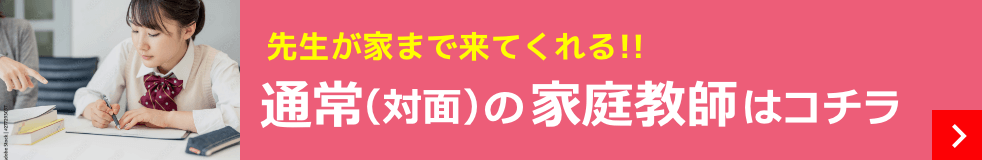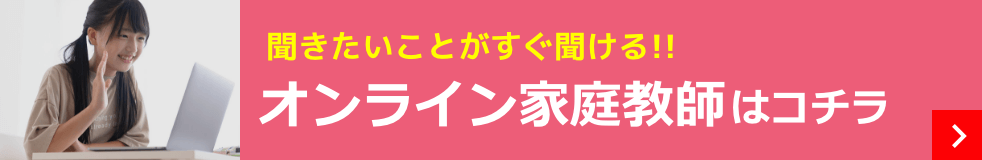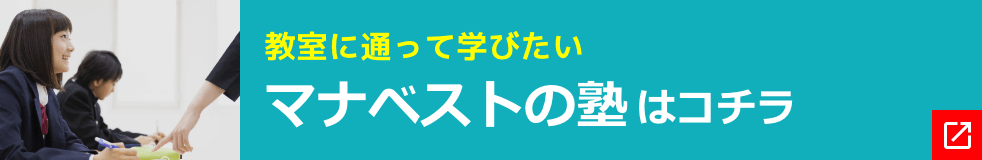【子育て】
受験生とのかかわり方
学年が上がり、いよいよお子さんが受験生になられた親御さん。
お子さん自身の不安やストレスは言うまでもありませんが、
親御さんとしても不安だったり心配だ...
【数学・雑学】
セミと素数の意外な関係!?
2024/04/24
「1と自分以外の数字で割り切れない数字」を「素数」といいます。
たとえば、2、3、5、7、11…などは1以外の他の整数で割り切れないので、素数ですね。
...
【全学年対象】
勉強の「割れ窓理論」
2024/04/23
今回は、“最初に少し苦手という印象を抱いた教科が、時間を経るごとにどんどん苦手になっていく”
ということについて考えたいと思います。
治安...
【数学】
共通点と相違点
2024/04/22
数学のセンスを磨くには、書かれていることの【共通点】と【相違点】に着目することが第一歩です。
共通点・・・2つ以上のものの、それぞれが共に持つ性質
...
【子育て】
○時間勉強すれば…
2024/04/21
誰もが「○時間勉強すれば…」と、“時間”を勉強の基準にしたことがあるのではないでしょうか。
・毎日○時間勉強するのがルール!
・○時間勉強すれ...
【全学年対象】
マルチタスクも一長一短
2024/04/20
マルチタスクとは、複数の作業を同時にこなすことです。
たとえば部下数人に指示をだして複数のプロジェクトを同時に管理したり
デスク上で複数の作業を並行し...
【全学年対象】
昨日の晩御飯何だっけ?
2024/04/18
「昨日の晩御飯何だっけ?」
誰もが思ったことがあるこの言葉。
人間の記憶は悲しいもので、昨日のことでさえ忘れてしまいます。
もちろん忘れてし...
【新受験生対象】
四月中にやるべき必勝法3選
新学期がはじまって、ようやく新しいクラスにも慣れてきたのではないでしょうか?
「四月だからまだ大丈夫だよね!」なんて話し合っている友達も、
既に陰では受験...